
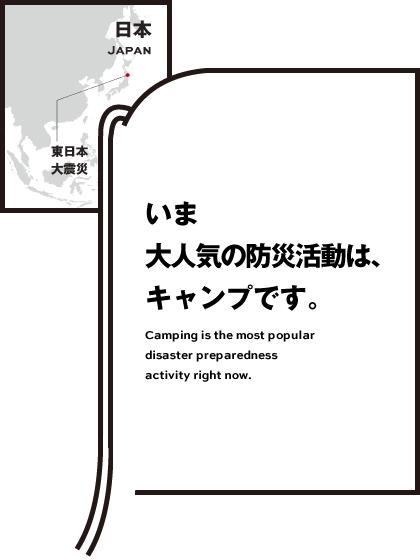 いま大人気の防災活動は、キャンプです。
いま大人気の防災活動は、キャンプです。
-


- 災害発生前
- デザイン
- NPO法人プラス・アーツ
- レッドベアサバイバルキャンプクラブ
- レッドベアサバイバルキャンプ

大人気のプログラム、ロープワークの実技講習。
「キャンプ」から、災害時に生き抜く力を学ぶ。
2011年10月にNPO法人プラス・アーツが神戸市立自然の家で開催した1泊2日の「レッドベアサバイバルキャンプ」には、17組60名の家族が参加。救急救命の講習やロープワークの実技指導、段ボールとビニールシートでシェルターを作るなどのワークショップを体験した。これは家族で自然を楽しむためのものではなく、その名の通り、災害を生き抜くサバイバルの技を身につけるためのキャンプだ。
同法人が展開する防災訓練プログラム「イザ!カエルキャラバン!」が伝えるのは、けが人を運んだり、消火の仕方を学ぶといった、対処療法的なスキルや知識。最大で2000か所の避難所に約47万人が避難した東日本大震災の現実を受け、こうしたスキルだけでなく、避難所などの過酷な環境の中で、災害を生き抜く根本的な力を養うためにはどうしたらいいかと、同法人が考えたときに浮かんだキーワードが「キャンプ」だった。
アウトドアのスキルは、そのまま災害時のサバイバルにも応用できるうえに、限られた資源と環境の中で過ごすキャンプの場では「疑似避難生活」を体験することもできる。
「たくましさ」と「2つのソウゾウリョク(創造力と想像力)」の二つの力を育む「レッドベアサバイバルキャンプ」は、2011年から毎年秋に神戸で開催され、2012年からは福島県いわき市で開催されるなど、徐々に広がりを見せている。
地域に定着し、持続的に発展するための
サポート役へ。
「レッドベアサバイバルキャンプ」は、地域の担い手の思いや防災面の課題をふまえ、アレンジされつつ各地で開催されている。
たとえば福島県いわき市では、東日本大震災で断水に苦しんだ地域住民たちの経験をもとに、水の運搬に関連するワークショップを共に考え、組み込んでいる。
岡山市では、同法人の理事長を務める永田宏和氏の講演を聞いた市内の高校生が、文化祭で開催したいと依頼。通常1泊2日のキャンプの内容をデイキャンプにアレンジし、高校生たちが講師となって、文化祭に来た子どもたちにスキルを教えるプログラムとした。
地域に防災の取組みを定着・継続させていくために、システムやノウハウを提供するだけでなく、地域と一緒に課題を考え、その想いを反映したプログラムを形にしていくという同法人の方針が「イザ!カエルキャラバン!」同様、このキャンプにも反映されている。
市民がクリエイターになって広げていく、
新しい防災活動。
「イザ!カエルキャラバン!」におもちゃのかえっこシステムがあったように、「レッドベアサバイバルキャンプ」にも子どもを夢中にさせる“仕掛け”がある。各プログラムに挑戦し、技をマスターすると、アートディレクター・寄藤文平氏デザインのオリジナル缶バッチがもらえるというもので、様々な「技バッチ」を中心に全部で40種以上ある。
この子どもの積極性を引き出すバッジの仕組みは、デザイン・クリエイティブセンター神戸が主催し、永田氏が講師を務める「+クリエイティブゼミ」の受講生から出たアイデア。
もともと「レッドベアサバイバルキャンプ」は、2011年5月から始まったゼミの課題として企画が練られていったもので、現在でも、ゼミ生を中心に学生や社会人などが「レッドベアサバイバルキャンプクラブ」の部員として毎週木曜日に集まり、秋のキャンプやイベントなどにむけて企画や準備を行っている。
初期からのメンバーの一人は、「阪神・淡路大震災の被災経験をプログラムに反映させるだけではなく、参加している若い人たちにも体験を伝えることができ、神戸ならではのプロジェクトに関わっているというやりがいを感じる」と話す。市民が“クリエイター”となって防災プログラムを生み出し、育てていく「レッドベアサバイバルキャンプ」は、市民と防災との関わり方の一つの新しいモデルとなる可能性を秘めている。









