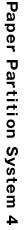
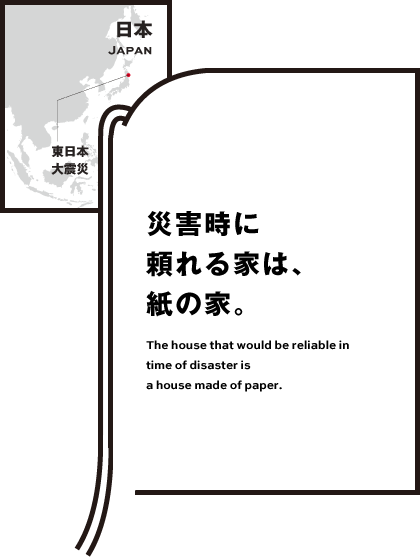 災害時に頼れる家は、紙の家。
災害時に頼れる家は、紙の家。
-


- 災害発生直後
- 建築
- 坂 茂
- 建築家、京都造形芸術大学教授
- Paper Partition System 4
震災を教訓に改良を重ねた、
間仕切りシステムの「完成系」。
「紙の建築家」として知られる坂茂氏が設計した避難所間仕切りシステム「Paper Partition System4(以下、PPS4)」は、東日本大震災の50か所の避難所で、約1800セットが設置された。柱・梁・ジョイントには紙管、仕切りに布を用いたユニットで、ずらりと組み立てられた姿は、プライバシーの確保という主目的だけでなく、見た目も美しく、整然とし、混乱の被災地においては「秩序が保たれている」という安堵を感じさせる。
簡単に組み立て・解体ができ、解体後は再利用やリサイクルが可能で、安価で、十分プライバシーが確保でき、自由に開け閉めでき開放的にもなる。このPPS4を坂氏は「避難所間仕切りシステムの完成形」と話す。名称の通り、4代目のシステムであり、改善を重ねた上でたどりついたものだ。
PPS1は2004年の新潟県中越地震の避難所のために作られ、寒さと夜間の電気を考慮して、屋根を付けた構造としたが、実際には子どもの遊び場など「特別な部屋」として使われることが多かった。05年の福岡県西方沖地震では、腰までの高さの仕切りを用意したが、プライバシーの確保までには至らなかった。この課題を解消するため、翌年には神奈川県の体育館を借りてスタディを行い、ここでPPS4の原型を作り上げている。震災の現場で課題を見つけ出し、平常時にもスタディを重ねるという氏の災害支援への信念がPPS4という「完成形」を実現させた。
「建築家の使命」を問い続ける。
災害に対して最初に坂氏が動いたのは1994年のルワンダの内戦だ。国連から与えられたシェルターが十分でなく、難民が毛布に包まり、震えている写真を見た坂氏は、国連難民高等弁務官事務局(UNHCR)のジュネーブ本部にアポなしで乗り込み、紙のシェルターを提案した。その案をUNHCRが受け入れ、コンサルタントとして、ジュネーブやルワンダに赴いた。
その後、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震、スマトラ島沖地震、四川大地震、東日本大震災と世界各地の災害現場で、仮設の住宅や施設、避難所間仕切りを作り続けている。世界中の災害に対して飛び回るその原動力は、「建築家の使命」を貫き通す氏の信念にある。
「医者や弁護士は常に弱者のために働いている。一方、建築家は金持ちのシンボル的なものを作ることが多い。建築家は社会のために何ができるのか。建築家の根本的な使命は『よりよい住環境を作ること』。それはお金をかけた住宅でも、仮設住宅でも同じように考えなければならない」と坂氏は話す。
時には自己の資金を持ち出してまでも避難所の間仕切りや仮設住宅を提供するその活動は、「災害支援」という枠を超え、世界の建築家に対し、「社会的使命」を問い続けているプロジェクトでもある。


