
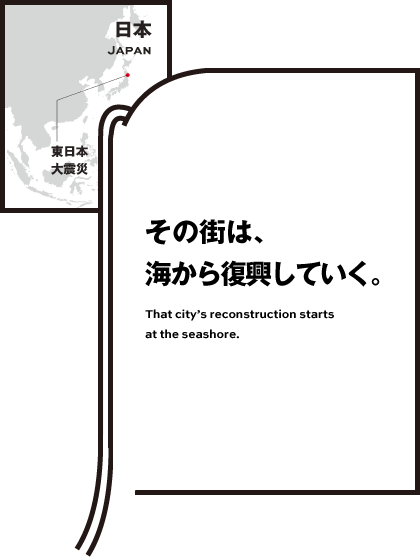 その街は、海から復興していく。
その街は、海から復興していく。
-


- 復興期
- 建築
- 一般社団法人アーキエイド
- 牡鹿半島支援活動
支援したい人と受けたい人を
全国規模でマッチングする。
アーキエイドの最大の特徴は、建築の専門家のサポートを欲している被災地のニーズと、支援をしたいと考えている全国の建築家や大学生のマッチングを行う「災害支援のプラットフォーム」を形成している点にある。その役割が最初に発揮されたのが、2011年8月に開催された「サマーキャンプ『半島“へ”出よ』」だった。宮城県石巻市牡鹿半島支援のため、全国から15大学の建築家と111名の建築学生が集まった。
キャンプ前には、東北工業大学の福屋粧子氏が中心となって、牡鹿半島にある大小30の浜を回り、その代表者と会って活動への理解を求めた。こうした準備を経て、各大学は浜に入り、フィールドワークやヒアリングなどを通して、住民と信頼関係を築いていった。同様のサマーキャンプは翌12年にも行われているが、住民と行政との仲介を務めたアーキエイドの存在がなければ、これだけ大規模の支援活動は難しかったと思われる。
日頃から築いていたプロフェッサーアーキテクト同士の密なネットワークの存在とともに、阪神・淡路大震災の復興期に建築家が十分にその職能を果たせなかったことへの反省が早期の立ち上げにつながったと、アーキエイド事務局長の本江正茂氏は話す。過去の震災からの教訓が今回の震災に活かされた形となった。現在も月に一度、「半島支援勉強会」として東京に各大学の教授や学生が集まり、各浜の復興の進捗状況の報告、課題などを話し合い、牡鹿半島全体の復興の情報交換をしながら継続した活動を行っている。
どこに住むかより、どのように住むか。
防災集団移転促進事業では国土交通省の直轄の調査が行われているが、この調査が「高台移転を促す」ものであるのに対し、牡鹿半島支援活動では「高台移転してどのような暮らしをしたいのか、どのように低地を活用していきたいのか住民から直接意見を引き出し、計画に反映させる」調査を行うことを当初からの目的としていた。ここで活躍したのは学生たちだった。「上から目線ではなく、教えてほしいという学生の姿勢が、住民の本音を引き出した」と福屋氏は語る。専門家に対しては敷居が高いと感じて話せないことも、孫や子どもと同じ世代の学生たちには住民は気軽にいろいろなことを話せたという。
震災前の浜の特徴、ライフスタイル、建物、風景などを学生たちは住民に丁寧にヒアリングし、『浜のくらしから浜の未来を考える』という冊子にまとめた。今の状態と昔の状態をきちんと把握しなければ、将来のことは考えられない。住民の声を吸い上げ、復興計画に反映していくという地域に寄り添ったきめ細かい支援活動は、学生たちの参加により実現できた側面が大きい。
「建築」という枠を越え、
街づくりを支援していく。
2013年8月、牡鹿半島の桃浦で、桃浦浜づくり実行委員会が主催、石巻市、筑波大学、アーキエイドの共催で、「牡鹿漁師学校」が開催された。漁師という浜の歴史と文化を担う人材づくりを支援するための学校に県内外から定員の15名が応募し、座学や船に乗って海に出るなどの実技もあわせた濃密な授業が3日間にわたって行われた。
「牡鹿漁師学校」の構想は、2011年のサマーキャンプ時より、住民から提案されていたという。牡鹿半島のどの浜でも、高齢化や後継者不足によって、漁業の衰退が懸念されていたが、震災によって一気にこれらの問題が表面化した。桃浦で生まれ、育ち、漁師として船に乗っていた甲谷強氏は、「工事により立派な港湾ができたとしても、人がいなければ、『浜の復興』にはならない。震災を機に、貝島研究室の皆さんと知り合うことができた。私たちだけではこのような学校は開催できなかったでしょう。皆さんの力を借りて、他の浜のモデルケースとなるよう、漁師の町を再興させたい」と話す。
過疎地にもともと起こっていた問題も含めて、住民とともに解決し、サポートしていこうという同研究室の想いが、桃浦住民による「牡鹿漁師学校」の実現につながった。
個々の住宅やランドスケープだけでなく、「浜の未来」をどう設計するか。住民と寄り添う長期的な支援のあり方はどのようなものなのか。アーキエイドの今後の伸展が、その試金石として注目される。




