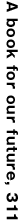
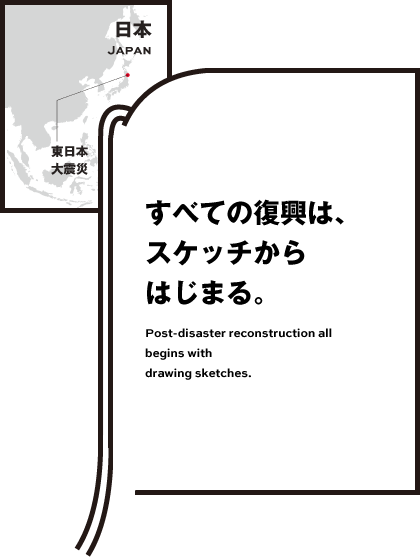 すべての復興は、スケッチからはじまる。
すべての復興は、スケッチからはじまる。
-


- 復興期
- アート
- 中田千彦
- 建築家、宮城大学准教授
- A Book for Our Future, 311

「A Book for Our Future, 311」の活動の原点となった学生たちのスケッチ
つぎつぎと実現させることで、
「復興が進行中」と発信する。
宮城大学中田研究室が行っている宮城県南三陸町長清水の復興支援活動「A Book for Our Future,311」の内容は多彩だ。2011年6月に現地でスケッチし、意見交換を行ったワークショップをはじめ、復興のシンボル「ながしずてぬぐい」の制作、漁業の長屋の建設、高台移転などについて話し合ったワークショップの開催。現在は、新たな産業として漆の植林を検討中だ。
震災直後は、甚大な被害の前に、建築家として何をすべきなのか、デザインに何ができるのか、中田千彦氏は悩んだという。そうした中、一つの“答え”となったのが、住民からの「スケッチを描いてほしい」という依頼だった。瓦礫の中にいると気が沈むばかりだから、学生の皆さんに「未来の長清水」の絵を描いてほしい。それが私たちの意識を変える一つのきっかけになるのではないか、という提案だった。
震災から3ヶ月後に、学生たちは瓦礫の中で各々が将来の町の姿を想い、半日スケッチをし、住民と意見交換を行った。このワークショップが、活動名と方針を決めた。地元の人とのやりとりから、無数のアイデアを重ねて、それらを束にし、必要な時に応じて引き出しせるような本(Book)。こちらが何かプランをもって動くのではなく、地元の人たちがしてほしいと思ったことを素直に返していく、それを積み重ねていくことが一つの支援の在り方ではないかという思いからつけたタイトルだった。その後の手ぬぐいの制作や長屋の建設などの活動は、この時のスケッチのアイデアを一つひとつ形にしていったものだ。
「私たちの活動が常に伸展し、”To be continued“にあることを示すことが、前向きな復興につながる」と中田氏は話す。Bookから引き出したアイデアを一つずつ実現していく過程が、多彩かつアクティブであり、その実績は、2012年度グッドデザイン賞の受賞など評価されている。
「自主的に復興するための手助け」という、
一歩引いた支援の仕方。
長清水では、東日本大震災の津波で37戸中34戸が流出。壊滅的な被害を受けながらも、早期の復興を望む住民の意欲は高かった。そうした住民から、地元の意思も十分理解した専門家として、防災集団移転促進事業を進める行政や土木コンサルタントとの仲介役になってほしいと、被災直後から中田氏に対して依頼があった。
当然、その役目を引き受けつつも、第三者が復興計画の間に入って齟齬が起きてしまったら、長清水のような小さな集落ではそれが早期復興への妨げになると考え、前面に出ることなく住民の後ろで寄り添うような形で支援を行ってきた。さりげなく住民に「今日の行政とのミーティングに出たほうがいいですか」と確認したり、また、直接聞かなくても住民の言葉や態度から出たほうがいいと判断した時のみ、会合に参加した。行政も土木コンサルタントも、中田氏と地元の信頼関係を承知しており、連携をとる形で、復興計画は進められているという。
「一方的な案や考えを押し付けるのではなく、繰り返し繰り返し、課題に対して最善を尽くし続け、必要とする人に『これでいいか』と問いかけるのがプロであり、それがデザインの本質」という中田氏の考えがベースとなり、決して前面に出ることなく、あえて一歩引いた「住民が自主的に復興するための手助け」という寄り添い方になって表れている。



