
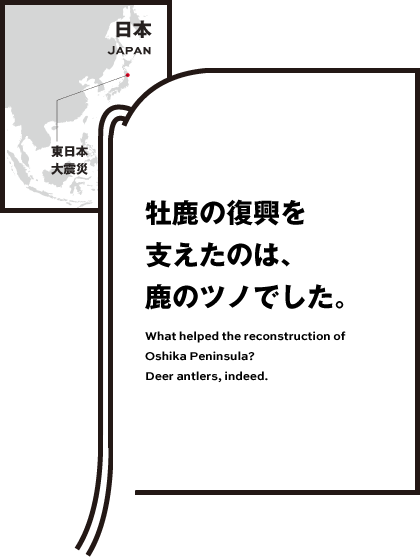 牡鹿の復興を支えたのは、鹿のツノでした。
牡鹿の復興を支えたのは、鹿のツノでした。
-


- 復興期
- デザイン
- 友廣裕一
太刀川英輔 - 一般社団法人つむぎや
デザイナー、NOSIGNER代表 - OCICA
「復興支援品」で終わらせない、
「地元のもの」にこだわる。
鹿角に切り込みを入れ、漁網を巻きつけたアクセサリーOCICA。宮城県石巻市牡鹿半島の牧浜の集会所に毎週火・木の10時から12時まで、30代~70代の地元の女性たち約10名が集まり、この個性的なアクセサリーを作っている。
2011年7月、避難所の状況把握を行うプロジェクトからの流れで、牧浜と出会った友廣裕一氏は、「支援を受けるだけでなく、自分たちも何かに貢献したい」「一人ではどうやって時間をつぶせばいいかわからない」という浜の人たちの声を聞き、「何か仕事を生み出せないか」と考えた。その際、こだわったのは「地元のもの」だった。なぜその場所で、その商品だったのかというストーリーがなければ、作る方も買う方も、魅力や愛着を感じてもらえず、長続きしないと考えたという。そこで、牡鹿半島に多く生息している鹿の角と、浜の生業である漁業で使われる漁網に目をつけ、それらの素材からこのユニークなアクセサリーが生まれた。
震災後、多くの「復興支援品」が生まれたが、ほとんどは一過性のものとして続かなかった。そうした中、OCICAは2013年8月現在、約1,000万円の売上を上げ、浜の女性たちの生活費の支援となっている。
素材にも、デザインにも、オリジナリティを。
OCICAが今でも売れ続けている理由として、地元の素材を使った点以外に、OLIVEサイトも立ち上げたNOSIGNERの太刀川英輔氏のデザインが大きく寄与している。
友廣氏の意図を理解し、単に外見にこだわるのではなく、牧浜であるからこそ意味があるデザインでなければならないと考えた太刀川氏は、まずは牧浜の集会所で作り手の女性たちとともにワークショップを行い、そこから出た意見を参考にデザインを練っていった。
鹿の角は、アクセサリーをつくるうえで難しい素材だったという。角の真ん中の髄はスのようになっている上、表面はごつごつし、色や形も一定ではなかった。
試行錯誤する中で、輪切りにし、スになった部分をくり抜いて、ドーナツ型になった鹿角に漁網をかけたところ、見覚えのある形になった。アメリカのネイティブインディアンに伝わる装飾品で、悪い夢を食べると言われている「ドリームキャッチャー」の形だった。
古来から鹿の角は「水難のお守り」という由来もあり、それが悪夢(=津波)を食べるお守りの形となって、津波の被害を免れた集会所で、女性たちの手から生み出される…。こんなストーリーが自然に編みだされたという。「いいデザインが生まれる時には、ある種のコンセプトとコンセプトが一つの意味に集約される瞬間があって、まさにこの時がそうだった」と太刀川氏は回想した。

- 鹿の角のスの部分を取り除いた後、丁寧にヤスリにかけていく。

- 不揃いの角をやすりをかけて成形していく。作業も慣れてくれば、おしゃべりも弾む。

- 慣れた手つきで、漁網を鹿の角の縁にかけていく。

- アクセサリーの台紙には、作り手の屋号の判子が押されている。
経済支援だけでなく、コミュニケーション支援も。
素材とデザインにこだわった友廣氏だが、OCICAを無理に存続させることは考えていないという。OCICAからは一定の利益が出ているが、「つむぎや」はこの利益に依存するような運営を行っていない。その理由を、「浜の人たちが変わろうとした時に、僕らが足かせになってはいけないから」と話す。
もともとOCICAは経済支援だけを目的として設立されたわけではない。震災前、牧浜は世帯数23戸の小さな集落で、漁港には牡蠣処理場があり、牧浜の外からも殻むきの作業のために通う人がいるなど、牡蠣養殖業が盛んだった。しかし、東日本大震災では防波堤や牡蠣処理場が流され、浜は主要産業を失った。被害戸数は12戸と約半分の家がなくなり、住民は家が無事だった者と、仮設住宅に住む者に二つに分かれ、家を失った人への気兼ねから以前のような交流は途絶えがちだった。
しかし、制作の作業後の「お茶っ子」というOCICAのお茶飲み会では、持ち寄った手作りのお惣菜をつまみながら、家が無事だった者も失った者も、震災以前のように談笑し、これを楽しみに通う女性達もいる。「手作業」の創出だけでなく、「コミュニケーション」の再生も兼ねている点が、OCICAの被災地支援の本質といえる。



