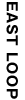
 復興のヒントは、先進国ではなく途上国にありました。
復興のヒントは、先進国ではなく途上国にありました。
-


- 復興期
- デザイン
- 髙津玉枝
岩切エミ - 株式会社福市代表取締役
デザイナー - EAST LOOP
数ヶ月先のことまで考えた支援を。
東日本大震災の被災地の女性たちに「手仕事」を提供している「EAST LOOP」。髙津玉枝氏がこの事業を立ち上げたのは、自身が経営しているフェアトレード事業がきっかけだった。
生活環境が悪く、仕事もないが、容易にその土地を離れることができない。途上国と被災地の状況は似ている。以前訪ねたネパールのタルー族の女性が、「ただ支援のお金をもらって生きるのではなく、自分たちで仕事をして誇りを持って生きていきたい」と話していたように、災害を生き延びた人には、絶対に“仕事”が必要だと考えたという。「避難所や仮設住宅ですることがない毎日を送っているうちに、何の役にも立っていない、どうして自分が生き残ったんだと思う人が出てくるのではと思いました」と髙津氏は話す。実際、阪神・淡路大震災から2~3年経った神戸市では自殺者がそれまでの1.5倍に急増した。18年前のこの地震で被災した髙津氏は、緊急物資を送ることが支援の主流となっていた2011年4月に、数か月先の被災地のことを考えていた。
被災地に新たな仕事を作り、新たなものを作り出す。そしてそれを買ってくれる人がいて、つながりができるという「ループ」。避難所・仮設住宅にいる女性たちが、誰かのために作る手仕事「EAST LOOP」は、2011年7月に立ち上がった。

- 株式会社福市が全量買取となっているEAST LOOP。本体価格の半分が作り手に渡っている。

- 最初に教わった後は、各々のペースで編んでいく。

- 商品には作り手の名前が記されており、作り手宛にFacebookからメッセージを送る事ができる。
商品開発に、デザイナーの「色」は
あえて出さない。
当初から髙津氏は、手仕事の商品としてニットの小物を考えていた。ミシンなどの機械がなくても、かぎ針が一本あれば、場所や時を選ばず、自分のペースで編むことができる。フェアトレードの商品を扱ってきた経験ならではの発想だった。
デザインはファッションデザイナーの岩切エミ氏に依頼。これまで編み物をしたことがない人も作るため、高度なデザインは望めない。それでも万人受けして、買ってみたいと思わせるもの。そのぎりぎりのせめぎあいを、岩切氏のデザインが埋めていったが、そこにはあえて「自分の色」を出さなかった。自分の役割を「被災地と消費者をつなぐためのデザイン」と割り切った氏の想いが、ハート型のブローチを生み出した。丸型や四角型と違い、多少いびつな形でも、それはハートの“個性”として消費者は認識してくれる。デザイン性と作り手である被災者のおかれた環境の双方に配慮したヒット商品となった。
被災地の自立をうながす、「期間限定」の支援。
ニット小物の作り手を募集する際に、他県からの“ヨソモノ”がやるよりも、信頼を得ている地元の団体の力を借りた方がよいと考えた髙津氏は、沿岸部の支援拠点となっていた岩手県遠野市にある「NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク」に協力を求めた。
同NPO代表の菊池新一氏は、被災から数ヶ月して、虚無感や無力感に陥る被災者の姿を見て、髙津氏の語る「手仕事の必要性」を実感し、「EAST LOOP」に賛同したという。同NPOでは、被災した住民を社員として雇用し、仮設住宅を一軒一軒回って、必要なものなどをヒアリングし、被災者との信頼関係を築いていた。このNPOなどの協力のおかげで、岩手から宮城までの沿岸部の6地域から約200名が作り手として登録した。
また、いつまでも支えていたら本当の自立にはならないという思いから、当初からこの事業は1年間の期間限定とし、その後、継続したい人がいれば、事業を現地に譲渡すると決めていたことも、この事業がカウンターパートを必要とした理由の一つだった。
ピーク時の作り手は、100名程度だったが、現在は50名程度。他の人たちは、震災前の職業に戻ったり、または違う職に就いて「卒業」されたという。これこそ髙津氏の目ざした形だった。
結果的に1年経っても復興がほとんど進まなかったため、2年間継続した。2013年度中に同NPOが受け皿となった新しい組織に事業を譲渡する予定だという。“期間限定”ながらも、「EAST LOOP」は、2013年3月までに5,000万円以上を売上げ、作り手には2,500万円以上が支払われている。
